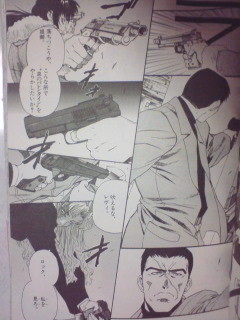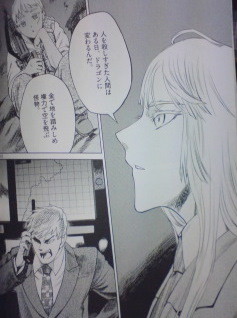メリークリスマス!!
閑話休題、先日発売された『BLACK LAGOON』13巻。前巻から2年以上空いていますが、それ以前がよっぽど空いていたので、むしろ早いと思ってしまいますね。不思議不思議。
さて、そんな13巻では、前巻から始まった〈五本指〉編がちょうど終わりました。黒人の大男ばかりを狩るスーツ姿の女五人組、〈五本指〉が起こした事件の中で、ラグーン商会のボスにして知的なタフガイ・ダッチの知られざる過去が仄見えたり、レヴィの意外な面倒見の良さが現れたり、表の世界にシマを広げようとしてるバラライカが苦労したりと、血と硝煙でけぶるロアナプラに、また新たな一面が見えてきました。で、そんな事件もケリがつき、〈五本指〉の一人だったルマジュールをロアナプラに引き込んだレヴィ。仲間に見捨てられたルマジュールを生き残らせ、ホテル・モスクワとの和解を仲介し、街での生計や商売道具も見繕ってやるという、普段のガラッパチで刹那的な彼女からは思いもよらない面倒見の良さに、ロックも驚きました。
「随分と彼女の世話を焼くじゃないか。何が気に入った?」
「別に。」
「やっぱり慕われちゃ放っておけないか?」
「……殺しで飯を食ってるからよ。一つ、決めてることがある。
星の廻りで敵味方になるのは運命だが——良くしてくれるやつには良くしてやる。邪険にして無駄に恨まれることはねえ。
正面から撃たれても、背中から撃たれることはねえという—— ちょっとした願いだ。」
(13巻 p95,96)
きったはったの緊張感の中で生きているからこそ、その緊張を緩めて精神を休めさせられる関係性が必要だ。レヴィはそう言うのです。
彼女のそんな考えにロックは、「孤独じゃないと生きていけないタイプなのかと思ってた」と冗談半分本気半分で軽口をたたきますが、それをレヴィは静かに訂正しました。
何処に居たって孤独は毒だ。
それに――
信用と信頼は似てるが少し違う。頼るのは好かないし、頼られても困る。
(13巻 p97)
信用と信頼。
この二つのが違うものであると評するのを私が見たのは、これが二回目です。一度目は、往年のライトノベル『無責任艦長タイラー』の中でした。
脱法的な輸送任務を依頼するにふさわしい人材として、スナガは悪友であるバーミンガムをススムに紹介するのですが、そのバーミンガムは「ちょろまかしのバーミンガム」とあだ名される、物資横領の常習犯。有能ではあっても遵法意識の極めて低い彼を紹介するときにスナガは、「信頼はしても信用はしない。そんな相手」(大意)と冗談めかして言ったのです。
信用と信頼の違い。
当時『タイラー』を読んだ私は、「能力には信をおくが、心根にはおけない」というニュアンスを、幼心に感じ取っていました。
アウトローな感じ。能力ゆえに素行の悪さが見逃される感じ。悪友同士が軽口をたたき合う気の置けない感じ。そういう諸々もひっくるめてなんかカッケェと思い、いまだに記憶にガッチリ刻み込まれています。
ですが、レヴィの言わんとしているところは、そんなブロマンス的ハードボイルドさとは違うようです。
「俺はお前を頼るし、頼られたいと思ってる。信頼しろよ。」
「おう、信用してるよ。」
(13巻 p98)
ロックの「信頼しろよ」という言葉に「信用してるよ」と、わざわざ傍点を振って違いを強調して返すのです。ここには、『タイラー』のそれよりだいぶ虚無的で冷血的なものがあるように感じます。
彼女の言わんとしているところは、まさに「信『用』」と「信『頼』」の違いで、「用いる」というのは自分を主体にして補佐的にあるいはビジネスライクに相手に信を置くこと。それに対して「頼る」というのは、ある場面での主導権を相手に任せた上で信を置くこと。そんな、自分と相手のどちらに主体・主導があるのか、という点に差異があるように思えるのです。
それはとりもなおさず、このロアナプラという明日をも知れぬ危険な街で、彼女がどう生きてきたか、どう生きていたいかという信念、生き様を表しています。
一人では生きていけないが、自分や場面の主導権を誰かに握らせてはいけない。「一個きっかり」の命、どうせ死ぬなら後悔しない死に方で、「正面から撃たれ」た方がマシ。
群れてはいても一匹狼。そんなアウトローの生き方をまざまざと感じさせます。
レヴィの言葉のの使い分けに、ロックがどう反応をしているのかは描かれていませんが、少なくとも先に「信頼」という言葉を使ったロックは、その言葉を彼女と同様にはとらえていないだろうし、あるいは彼女と同じような信念では生きていない。
ならばロックの信念は何か。生き方は何か。
ロベルタ編が終わったときの記事でも書きましたが
yamada10-07.hateblo.jp
yamada10-07.hateblo.jp
端的にロックは、「面白さを求める」という享楽的な信念のために命を張っています。その命は、自分のものもだし、他人のものも。
その後も各エピソードが描かれるたび、ロックのそのような面は表現されていますが、本エピソードのエピローグでも、張とカジノでルーレットに興じているときの問答で以下のようなものがあります。
「……依頼人に言われた。俺は——誰かの運命の、その行方が見たいんだと。」
「裁くのか? 泰山府君の様に。」
「それは俺の柄じゃない。だが、俺が指を添えることで——その人の運命のその先へ、辿り着くことができるかも。」
(13巻 p126,127)
ロックの望む「面白さ」とは、誰かの運命の行く末。それがどこにいくか。自分が面白いと思えるところに収まるのか。それを見たい。
ロックは何でも屋のラグーン商会に属する中で様々なトラブルに首を突っ込み、当事者のどちらにも肩入れせず、あるべきところに収めたい。それが彼の「面白さ」。昼でも夜でもない「夕闇」に立ち続けることでロックは、人の運命の行方を砂かぶりで見ようとするのです。
でもそれは、非常に危うい立ち位置。
こう考えることはないか? 誰かの運命を変えたら――
お前自身も飲み込まれるかもしれん、傍観者ではなく… その当事者になって。
俺は慎重なタチでな。そういう賭けは好ましくない。
(13巻 p128)
張の忠告とも警告ともつかない言葉ですが、それにもロックは、例の悪い顔で返すのです。
ミスタ・張。そこまで肉薄しなけりゃ――… 誰かの人生のその先は、見えないんですよ。
(同上)
彼自身は当事者になりません。あくまで、運命と対峙している誰かに指を添える傍観者。場の主役は相手に任せたまま、複雑な力場にほんの少し力を加えて状況を動かそうとするもの。
だから彼は人を頼ります。場の主役は自分じゃなくていいから。
主役なんてくそくらえ。自分はそれを最前列で楽しめる観客でありたい。
あくまで自分は傍観者でいる。でもそれは当事者のすぐ隣。他人を呑み込む運命のすぐ隣。一歩踏み外せば簡単に奈落へ転落する際であろうと、そこでなければ楽しめないものがあるなら、自分はそこに立つ。
それがロックの信念なのです。
「信用」と「信頼」の違いから、ロックの信念にまで話が脱線していきました。おかしいな…タイラーの話をしてるときはこんな風になるとは思ってなかったんだけど……
とまれ、また一歩ロアナプラのトラブルバスターにして、地獄の舞台のVIPシートギャラリーに近づいたロック。さあ14巻はいつになるかな……
一言コメントがある方も、こちらからお気軽にどうぞ。