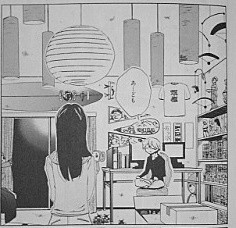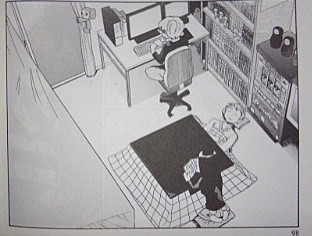とめはねっ! 鈴里高校書道部 7 (ヤングサンデーコミックス)
- 作者: 河合克敏
- 出版社/メーカー: 小学館
- 発売日: 2010/09/30
- メディア: コミック
- 購入: 10人 クリック: 192回
- この商品を含むブログ (72件) を見る
書の甲子園優勝校の豊後高校に馬鹿にされたように思った望月が、かけもちしていた柔道部を辞め書道部一本に絞ろうとしたときに、部長ひろみが言った言葉ですが、曰く、書にはその人の個性が出る、柔道を辞めては望月の個性が薄れる、書道に練習量は大切だがそれだけではなく、自分が本当に書きたい書を見つけることも大事なのだ、と。
ひろみや顧問影山にとっては、彼女が練習量を増やすより、柔道を続けて「個性」を残した方が書道にはいい影響があると判断したわけですが、わたしは別に望月が柔道を辞めたところでそれが彼女の個性の消失に繋がるとは別に思いません。「高校柔道で優勝しながら書道部を掛け持ちする少女」と「高校柔道で優勝する実力を持ちながらすっぱり辞めて書道部に絞った少女」、どちらが個性が強いかなんて比較のしようがないと思います。個性と言うなら両方とも個性でしょう。
まあ個性が何なのかという話は措いといて、練習だけではなく個性・才能・その人らしさ・その人が生まれながらに持っているもの・後天的に獲得したものも、書道にとっては大事だという話は、実はこの望月こそが体現しているのではないかと思うのです。
なにしろ彼女、柔道部と書道部を掛け持ちしているという状況で、柔道にせよ書道にせよ人(一つの部活に真面目に打ち込んでいる高校生、ということですが)並み以下の練習量でしかないのですが、弱冠高校一年生で高校柔道で二度の優勝を果たしているのです。これを才能、天賦のものと言わずしてなんと言いましょう。才能が、個性が努力を駆逐しています。
彼女が豊後高校の倣岸な態度に腹を立て、彼我の練習量や現段階での実力の天地の差を知りながらやる気を燃やしたのも、少ない練習量でも全国制覇をすることはできるという自分の経験からくるものでしょう。というか、それがなくてはあそこまで立派な啖呵を切ることはできません。「やってみなけりゃわからない」というのは若者の特権ですが、それを言えるだけの経験が彼女にはあるのです。
才能は、個性は、練習量を覆せる。少なくとも柔道においては、望月はそれを証明しています。果たしてそれが、書道でも見せられるのでしょうか。ただ彼女は、その気性と運動神経からか、力強い書体や、全身を使って書く大字書に秀でているというのは既にこれまで描写されています。これもまた、個性でしょう。才能でもありますけど。
次巻予告では、かな書で縁が覚醒!とのコピーがありますが、彼の柔和な性格と、祖母の手紙の文字を真似て日本語を書いていたという過去も、また彼の個性でしょう。才能でもありますけど。
ただ、この「練習(=努力)に対する個性(=才能)の優位さ」の強調の仕方は少々過剰なところがあるようにも感じ、このような「ある思想が他の思想より優位にある」ということを少々一方的な形で描くのは前作『モンキーターン』でも見られたものなので、河合先生の、それこそ「個性」なのかもしれませんが、これについてはまた別の記事で。
ちなみに、この作品で三番目にかわいいのは望月、二番目は京都の大槻、一番かわいいのは縁の祖母だと思います。異論はそこはかとなく認めなくもない。
「ネウロ」の松井先生も言ってましたが、若い頃が想像できるおばあちゃんてかわいいと思います。
お気に召しましたらお願いいたします。励みになります。
一言コメントがある方も、こちらからお気軽にどうぞ。